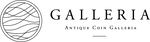フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨|フランス革命の女神マリアンヌが象徴する共和主義精神

▲ 種蒔く少女 オスカル・ロティ
フランス共和国の象徴であるマリアンヌが、豊穣の大地に種を蒔く姿が描かれたこのコイン。
フランスの近代貨幣史において、芸術性と思想が見事に融合したコインとして知られる種蒔く少女 5フラン銀貨は、コインの価値以上にフランス共和主義の精神までをも内包しています。
本記事では、その起源からデザイン、シリーズの種類までを丁寧に解説し、コインにまつわる歴史的背景と文化理解を深めていきます。
フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨

基本データ
| コイン名 | フランス 5フラン銀貨 |
|---|---|
| 通称 | 種蒔く少女 5フラン銀貨 |
| 発行年 | 1959年〜1969年 |
| 国 | フランス共和国 |
| 額面 | 5フラン |
| 種類 | 銀貨 |
| 素材 | 銀 |
| 発行枚数 | 152,476,026枚 |
| 品位 | Sv835 |
| 直径 | 29.0 mm |
| 重さ | 12.0 g |
| 統治者 | シャルル・ド・ゴール(Charles de Gaulle) |
| デザイナー | ルイ=オスカル・ロティ |
| KM | KM# 926 |
| 表面のデザイン | 左を向いている種を蒔く少女 |
| 表面の刻印 | REPUBLIQUE FRANÇAISE|O. Roty(フランス共和国|オスカル・ロティ) |
| 裏面のデザイン | 小麦・ドングリ・オリーブの小枝、額面、年号 |
| 裏面の刻印 | LIBERTE・EGALITE・FRATERNITE|5 FRANCS|年号(自由・平等・友愛、額面) |
| エッジのタイプ | レタリング |
| エッジの刻印 | LIBERTE EGALITE FRATERNITE(ラテン語で自由・平等・友愛) |
フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨とは?思想と芸術が結晶した硬貨

▲ フランス共和国とそれを取り囲むフランス共和主義者の寓意画 / 作者不明
ここでは、フランスの「種蒔く少女 5フラン銀貨」について解説いたします。
フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨とは?
フランスの「種蒔く少女 5フラン銀貨」は、フランス革命の後に誕生したフランス共和国のコインとして発行された象徴的な銀貨で、フランス共和主義の象徴「マリアンヌ」が種を蒔く姿が描かれています。
銀含有量は83.5%、重量約12g、直径29mm。国家理念と芸術性が融合したフランス近代貨幣の傑作です。
表面には、共和主義の象徴である「マリアンヌ」が、フリジア帽をかぶり、風にたなびくドレープの衣装をまとって種を蒔く姿が刻まれています。共和国の理想と未来への希望が象徴されるように彼女の背後には太陽が昇り、周囲には「RÉPUBLIQUE FRANÇAISE(フランス共和国)」の文字が刻まれています。
裏面には、オリーブ・オーク・小麦の葉で構成されたリースの中央に「5 FRANCS」と額面が配置され、その下に発行年が入り、周囲にはフランスの標語「LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ(自由・平等・博愛)」が記され、国家理念が反映されています。
フランス共和国の象徴「マリアンヌ」

▲パリ レピュブリック広場のマリアンヌ像
「マリアンヌ(Marianne)」は、フランス共和国を象徴する女性像であり、1789年のフランス革命以降、国民が築き上げる新たな政治体制の理念を体現する存在として定着してきました。
その名は、庶民に多く見られた女性名「マリー」と「アンヌ」の組み合わせに由来するとされ、王政を否定し民衆の力によって成立した共和国を、母のように支える象徴的な人格として捉えられています。現在でも彼女は郡庁や市庁舎、彫像や絵画、切手やコインにいたるまで、数世紀にわたりフランス共和国のヴィジュアルシンボルとして用いられています。
「種蒔く少女 5フラン銀貨」に描かれるマリアンヌは、フリジア帽をかぶり農民のような姿で右手に種を持ち、朝日を背景に大地に向かって種を蒔いています。
フリジア帽は、もともと古代ギリシア・ローマ時代に解放奴隷が自由を得た証としてこの帽子を被りました。このことから、フリジア帽は次第に「自由人の証」「専制からの解放の象徴」として象徴化していき、帽子を被ることで自由・平等・博愛の精神を掲げ、王政や特権階級への反抗を示す象徴となっていったのです。
また種を蒔き背後に朝日が昇るというこの構図は「共和国が未来に理想をまき、希望を育む」姿を象徴しており、単なる農耕の比喩を超えて、政治的・思想的な意味を帯びています。
この姿は単なる農作業の比喩ではなく、「国民が自らの力で大地を耕し、未来に芽吹く種を蒔く」という福音的で政治的なメッセージを含んでいるのです。
デザインを手掛けたのは象徴主義の巨匠オスカル・ロティ

▲オスカル・ロティ 1900年
オスカル・ロティ(Oscar Roty)は19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスのメダル彫刻の大家であり、アール・ヌーヴォー期に活躍した著名な彫刻家です。1875年にローマ賞(Prix de Rome)を受賞し、1888年にはフランス美術アカデミーの教授となるなど、当時の美術界で高い評価を得ていました。
ロティの作品は単なる装飾にとどまらず、深い精神性と理想を宿すものでした。数多くのメダルや記念貨幣を制作し、その卓越した技術と芸術性は当時のフランス芸術界に大きな影響を与えています。
ロティの代表作「種蒔く少女」は オスカル・ロティ財団(Fondation Oscar Roty )の解説では、彼の作品が「ヴィーナスや春神のイメージと接続しながら、生命力と精神性を象徴する図像」として位置づけられています。
その図像は、理想化された美しさ、静けさの中に秘められた動き、そして未来への希望という寓意を織り込みながら、単なる貨幣デザインを超えて物語性を帯びています。動きと感情を巧みに融合させたその表現は、20世紀初頭から中期にかけての貨幣芸術に深い影響を与えました。
特に、アメリカのアドルフ・ワインマン(Adolph A. Weinman)が1916年にデザインした「ウォーキング・リバティ」には、動きある理想の女性像という点で「種蒔く少女」との明確な類似性があり、多くの研究者が影響を指摘しています。

▲アドルフ・ワインマンがデザインしたアメリカ ウォーキングリバティ ハーフダラー銀貨 1916年
時代背景から読み解くフランス種蒔く少女 5フラン銀貨

▲フリジア帽をかぶったマリアンヌの像
こちらではフランスの「種蒔く少女 5フラン銀貨」が発行された当時の時代背景を中心に歴史とコインにまつわる文化的背景を紐解きます。
革命の胎動と共和国の誕生

▲ウジェーヌ・ドラクロワ『民衆を導く自由の女神』(1830年、ルーヴル美術館所蔵)
18世紀末のフランス社会は、極端な身分格差と財政破綻に苦しんでいました。王権を握るルイ16世の下、特権を持つ貴族や聖職者と、税負担に苦しむ第三身分(平民)の間には深い溝がありました。啓蒙思想の影響を受けた市民は、合理主義や平等の理念に目覚め、やがて旧制度(アンシャン・レジーム)への反発が沸点に達します。こうして1789年、フランス革命が勃発し、時代は大きな転換点を迎えました。
革命の進行とともに、1792年には王政が正式に廃止され、フランス初の共和政である第一共和政が成立します。この時、国王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットが断頭台にかけられたのは、王権神授説が終焉を迎えた象徴的な出来事でした。この政権下では「人民主権」「法の下の平等」「世俗的な教育」といった近代的価値観が制度として整備され、後のフランス共和国の基礎が築かれました。
しかし、理想に燃えた共和制は長くは続かず、ナポレオン・ボナパルトの台頭により1804年には帝政が再興されます。ナポレオンの治世は近代行政制度を整える一方、再び中央集権と軍事的独裁の時代をもたらします。1814年にナポレオンが失脚すると、王政がブルボン家(ルイ18世、シャルル10世)によって復活。ですが市民の間にはすでに自由と平等の価値観が根づき始めており、王政は再び民衆の抵抗に直面します。
共和制の確立と文化的自己認識

▲1898年7月10日に発行された新聞「ル プチ ジャーナル(Le Petit Journal)」に描かれた風刺画
1830年、七月革命によってシャルル10世が退位し、自由主義を掲げたルイ・フィリップによる七月王政が始まりました。しかしその政権も結局は保守化し、社会的不平等が解消されることはありませんでした。やがて1848年、民衆は再び蜂起し、第二共和政が成立。このときからフランスは二度と王政に戻ることなく、共和制国家としての方向を明確にしていきます。
共和制を安定させたのは、1870年にナポレオン3世が普仏戦争で敗北したことにより成立した第三共和政です。この政権は70年以上続き、フランスに近代的民主主義を定着させました。「普通選挙制度、教育の世俗化、言論の自由」などの法制度が整備され、市民社会の成熟が進みます。フランス人が「共和国」という体制に誇りと帰属意識を持つようになったのも、この第三共和政期においてでした。
この時期はまた、国民的象徴の再構築が進んだ時代でもありました。19世紀末、マルセイユーズを国歌とし、7月14日を建国記念日とした第三共和政は、象徴となるものを探していました。そこで王の肖像に代わる“共和国の顔”として登場したのが、「マリアンヌ」と呼ばれる女性像です。
彼女は、自由と平等を象徴する人物として公共空間にあらわれ、法廷の胸像や切手、紙幣などを通して国民に深く根づいていきました。
そしてその延長線上に、「種蒔く少女(La Semeuse)」というもう一つの象徴的存在が現れるのです。
マリアンヌと種蒔く少女― 共和国が蒔いた未来の種子

▲オスカル・ロティ 種蒔く少女のデッサン画
「種蒔く少女 (La Semeuse)」のデザインは、彫刻家・メダイユ彫版家として知られるオスカル・ロティによって制作されました。
ロティは1887年農務省のためにメダルのデザインを手掛けるも完成には至りませんでしたが、そのデザインは後に「種蒔く少女」の原型となりました。2年後の1895年、財務大臣ポール・デュメールの指名により、ロティはフランスの新貨幣デザインを担当。使命は「共和国の理念と共和政体の思想を反映し、かつ時代の新しい価値観と調和する貨幣を創造すること」でした。
そこで、彼の代表作である「種蒔く少女」を制作。まさにロティの思想と技術の結晶であり、フランスの貨幣文化における不朽の名作として今日に至るまで高く評価されています。
「種蒔く少女」は、風に髪と衣をなびかせながら豊穣な大地に種を蒔き、頭には自由の象徴であるフリジア帽を被り、背後には朝日が昇っています。
実際、当初このデザインは一部で「アナーキズムを助長する」と批判されることもありました。しかし、ロティ自身はこの少女を「私たちが去った後に芽吹くであろう思想の種をまく存在」と語ったとされています。この言葉は、共和制の理念を広め、次世代へと繋ぐというメッセージとして、深く国民に受け止められました。
「種蒔く少女」はマリアンヌの変奏であり、静止した胸像ではなく、歩み、働き、未来を育てる“行動する共和国”の象徴です。王政の肖像が威厳と支配を示したのに対し、この少女像は労働と希望、思想と継承を語ります。それゆえ彼女は、19世紀末の共和政フランスにおいて、「国家の思想と美意識の結晶」として通貨という日常的なメディアに宿されるに至ったのです。
このデザインはその後長く用いられ、切手、1960年の新5フラン銀貨、さらには現代のユーロ硬貨にも継承されました。

▲「種蒔く少女 (La Semeuse)」がデザインされた切手
100年以上を経てもなお、「種蒔く少女」はフランス共和国が国民とともに歩み、未来に理想を託し続けることを示す、普遍的なシンボルとして光を放ち続けています。
「種蒔く少女」シリーズの特別なコインたち
「種蒔く少女」シリーズには“ピエフォー(piéfort)”とよばれる試鋳貨があります。
こちらでは3点の魅力的なピエフォーを紹介します。
限られた数しか存在しないピエフォー
「種蒔く少女」シリーズには、限られた数しか存在しない“ピエフォー(piéfort)”と呼ばれる試鋳貨があります。
通常の2倍の厚みを持ち、特別な記念用途や展示用として製造されました。起源は中世フランスにさかのぼり、14世紀ごろには王侯貴族や外国使節への贈呈用として製造されていました。フランス語の「Piedfort(重い足)」は、分厚く重みのあるその形状に由来します。
もともとは試鋳貨(エッセイ貨)の一種で、貨幣の金属組成やデザイン確認用に造られたものですが、時代が進むにつれ、希少性や美術的価値からコレクターズアイテムとしての側面が強まりました。特にフランス造幣局(モネ・ド・パリ)は19世紀末から積極的にピエフォー貨を発行し、現代ではフランス以外の国でも公式に記念硬貨として発行されています。
コレクターの間では、通常貨より流通数が少なく、素材や仕上げも高品質なものが多いため、高額取引されることも珍しくありません。特に「種蒔く少女」シリーズのピエフォーは、その芸術性と象徴性から人気の高い一品とされています。
5フラン銀製ピエフォー : 静謐なる共和国の威厳

5フラン銀製ピエフォーは、ピエフォーの中でも高い人気を誇る逸品のひとつです。
通常貨の2倍以上の厚みを持ち、重厚な銀95.0%の輝きが、ロティによる「種蒔く少女」の優美な姿を一層際立たせます。特に未使用(FDC)クラスの個体は年々希少性が高まり続けています。
銀の厚みと磨き上げられた鏡面仕上げで甦る様子は、まさに硬貨を超えた芸術です。
2フラン銀製ピエフォー : モダン・クラシックの調和

1979-1982年に発行された2フラン銀製ピエフォーは、近代鋳造技術と19世紀芸術の融合を体現したコインです。
銀92.5%、重量約17.8g、直径26.50mmのこの試鋳貨は、フランス国立造幣局(Monnaie de Paris)による極少量発行の記念版です。
柔らかな光沢と繊細な彫刻が、未来へ種をまく女性像にさらなる生命感を与え、手に取った瞬間から美術作品を所蔵するという満足感が味わえます。
2フラン金貨ピエフォー:「小さな傑作」に宿る共和国の精神

「種蒔く少女」が刻まれた2フラン金貨のピエフォー(Piedfort)は、フランス造幣局(Monnaie de Paris)によって限定的に製造された希少な試鋳貨です。素材は金92.0%(22金相当)、重量はおよそ30.9g直径は27mm前後です。
この金製ピエフォーは、ロティによる象徴的な「種蒔く少女」のデザインが小型の金貨に濃密に凝縮されており、圧倒的な彫刻精度と光の反射が醸し出す神々しさで、貨幣芸術の真髄を示しています。重厚な金の輝きによって未来への希望がより強く感じられます。
フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨の価格推移
フランスらしいエレガントなデザインのコインです。通常発行のものは発行枚数も流通も多く地金価格ほどで手に入れられます。
その中でも特にコレクションに適している、希少な<ピエフォー(倍厚)>銀貨を中心にご紹介します。
1960年 MS66

2024年7月28日$204で落札。
1968年 ピエフォー SP68
発行枚数は500枚と少ないですが、比較的手に入れやすい価格で見つかることもあります。

2025年7月15日に$600で落札。
種蒔く少女のその他のコイン
1897年銘 (1959年発行) パターン MS62
発行枚数わずか12枚とされている、非常に珍しい裏側が「50サンチーム」の刻印のパターン銀貨です。

2024年7月28日$204で落札。
1898年 Essei SP65
金貨製造のための試鋳貨(Essei)です。金貨用のダイの試作のため、大型になっています。

2019年8月15日に$26,400で落札。
銀貨に込められた信念と美――「種蒔く少女」の永遠の価値

▲オスカル・ロティ 『種蒔き女』1887年 蝋のメダルを板に貼った作品 オルセー美術館所蔵
フランス共和国の種蒔く少女5フラン銀貨は、美しいだけでなく、深い思想と歴史的背景を兼ね備えた稀有な存在です。
オスカル・ロティはコインの中に、彼らが去った後に芽吹くであろう思想の種を蒔く存在として、種を蒔く少女を描きました。共和国の象徴・マリアンヌが種を蒔く姿は未来への希望、そして努力と豊穣の象徴として人々の記憶に刻まれています。
この種はコインとなり、今、未来の私たちの手の中にあります。それはまるで種のように生活に溶け込み、日々の糧を自由に芽吹かせています
実用貨幣でありながら、美術品としての格を保ち、国家の理想を宿すこの銀貨はただの古銭ではなく、“思想と時代の化身”といえるでしょう。
また、同デザインを用いた他額面の銀貨や、希少なピエフォー金貨など、シリーズとしての深みと広がりも大きな魅力です。それぞれが異なる文脈と目的で発行されており、収集の楽しみは尽きません。
もしあなたが「フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨」を手にするなら、それは一枚のコインを所有するだけでなく、フランスの歴史、芸術、そして人間の理想、そして激動の革命者たちの夢を手にすることを意味します。
この銀貨は、時を超えて語りかけてくる、自由への静かなる福音のような存在です。
フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨にご興味はありませんか?
- 現在、フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨をお探しの方
- フランス 種蒔く少女 5フラン銀貨を保有していて売却を検討している方
- 何かアンティークコインを購入してみたいけれど、どれを買えばいいのかわからない方
今すぐLINEでギャラリアの専任スタッフにご連絡ください。無料でアンティークコインやマーケットの情報、購入・売却方法など、ご相談を承ります。