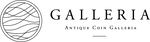【コイン収集の祖】フランチェスコ・ペトラルカとアンティークコイン収集の歴史

ペトラルカという名前は、世界史を勉強した人でもテスト勉強のために覚えたくらいの記憶しかないのではないでしょうか。
イタリアにおいては、ダンテやボッカッチョと並んで「イタリア文学の父」ともいわれる文学者フランチェスコ・ペトラルカ(Francesco Petrarca, 1304年7月20日 - 1374年7月19日)。コイン収集の世界では、彼こそがその祖とされています。
文学者がなぜコインの収集を始めたのか、ペトラルカの逸話も含めてご紹介いたします。
フランチェスコ・ペトラルカとコイン収集の歴史
イタリア文学の父の1人ともいわれるペトラルカ。その彼とコインの収集にどんな関連があるのか、不思議に思う人も多いと思います。ペトラルカと古代のコインの関係を探ってみましょう。
フランチェスコ・ペトラルカの歴史上の立ち位置
日本ではあまりなじみのないペトラルカですが、西洋における彼の歴史的な重みは計り知れません。歴史上におけるペトラルカの肩書は、「作家」「詩人」「文献学者」であり、「ルネサンスの先駆者」「イタリア文学におけるもっとも重要な文学者の1人」というタイトルも外せないのです。
そのペトラルカがなぜ、コイン収集というカテゴリーにおいて始祖とされているのでしょうか。
ルネサンスの時代を先取りしたペトラルカ
そもそも、「ルネサンス」という言葉は「再生」を意味します。なにが「再生」したのかといえば、中世には忘れさられていた古代の文化なのです。ルネサンス時代の人々は、古代の文化や芸術の洗練やレベルの高さを再評価することで、新たな文化を生み出したのです。
その意味においては、ペトラルカはまさしく「ルネサンスの先達」でした。なぜなら、彼の古代ローマへの傾倒は、病的といってもよいほどであったからです。
ペトラルカと古代ローマに対する憧れ・情熱
実際、彼自身も「古代ローマの書物や事象に対して、自分の欲望とおりあいがつかない」と告白しています。友人への手紙にも、「私はなによりも古代ローマの研究が好きだ」と無邪気に書いています。
古代ローマの書物がありそうな噂を耳にすれば躊躇なくその場に赴いて入手するのが常でした。中世に忘れされていた貴重な古代の古典が、ペトラルカをはじめとする文学者たちによって再び日の目を浴び、われわれの時代まで伝えられることになったのです。
その古代へのあこがれは、古代のコインを手元に置くという行為にも表れました。ペトラルカにとっては、渇仰する古代ローマ時代の人々が実際に手に取った貨幣に意味があったのです。つまり、コインに対する芸術的な興味は薄かったのでは、というのがペトラルカ研究家の一致した意見です。
前例なき「コイン収集」とペトラルカの苦心
コインの美観よりも、古代ローマ時代の遺物としてペトラルカが深い関心を寄せたコイン。それは前例のないことであったため、コインが鋳造された時代を見極めるのも簡単なことではなかったようです。
ペトラルカのもとに古代のコインを持ち込んだのは農民たち
書物については、ペトラルカ自身が欧州各地の修道院に赴いて入手するのが常でしたが、コインは当時のローマで農作業に従事していた農民たちによって持ち込まれることが多かったそうです。
現代のローマでも、地下鉄工事などで地面を掘ればさまざまな古代ローマの遺跡や遺品が出てくるのですから、14世紀のローマはさらに古代のローマを身近に感じるものが多かったのでしょう。ペトラルカ自身の言によれば、ブドウ畑で仕事をしていた農民が作業中に古代の貨幣を見つけてペトラルカのもとに運んでいたのだとか。
共和制から帝政におけるコインの羅列に苦悩
コイン収集というカテゴリーにおいても貨幣学という学問の分野でも始祖といわれるペトラルカ。しかし、前例がないことであったためにさすがのペトラルカも古代ローマ時代のコインを整理するについてはかなり苦労したようです。
つまり、ペトラルカ以前に系統立てて古代のコインを研究した形跡が見当たらないのです。
ペトラルカのコイン研究:『ローマ皇帝群像(Historia Augustae)』を参考にコインを特定
そこで、ペトラルカの研究はコインに刻まれたラテン語やローマ皇帝たちの肖像画から特徴を読み取ることが中心となりました。当時残っていた古代ローマの皇帝たちの伝記『ローマ皇帝群像』を参考に、皇帝たちの肖像を見極めていったそうです。
ペトラルカが熱中したこのコインの研究によって、コインをベースとした古代への新たなアプローチ法が歴史研究のひとつとして認められるようになりました。それまでは定かでなかった古代の著名人たちの真の姿が、コインから浮かび上がってくるようになってきたのです。
ヨーロッパでは、高名なローマ皇帝たちの肖像は一般常識として人々の頭の中に刷り込まれています。それは、ペトラルカをはじめとするルネサンス時代の古代の研究によって再生された、古代人たちの人間としての姿でした。
マントヴァを通過する神聖ローマ皇帝カール4世に捧げたコイン
ペトラルカのこれらの研究は、当時のエリートたちのあいだでも有名であったようです。
文人皇帝として有名な神聖ローマ皇帝カール4世は、プラハ大学などの創設を行った人でした。1354年、カール4世はイタリアに遠征します。そのとき、古代ローマに造詣の深いペトラルカをマントヴァに招聘し、古代のコインの真贋について相談したという記録が残っています。
ペトラルカは、厳しい冬の寒さもものともせずにマントヴァに赴き、カール4世に自分のコインコレクションの一部を進呈したそうです。長年のコレクションによって、いくつかの「かぶり」もあったのかもしれません。
ルネサンスの時代に花開いたコイン収集

画像:ボッティチェリが描いた男性の肖像。コインやメダルは富裕層のシンボルに!
ペトラルカが夢中になった古代ローマ時代の書籍とコインの収集は、ルネサンス時代を通じてエリート層たちの間に大ブームを巻き起こしました。その中には、歴史に名を残す著名な人々も数多く存在します。
法王からメディチ家の当主まで巻き込んだコイン収集ブーム
ヨーロッパ各地にある美術館や博物館を訪れると、美しい写本やアンティークコインが展示されていることも珍しくありません。これは、財力のある王侯貴族たちが美術品と同じように書物やコインを収集した名残なのです。
14世紀から15世紀にかけて、経済力を蓄えたイタリア貴族のあいだでまずこの風潮が顕著になりました。中世のローマ教皇たちは、古代ローマの遺物は「異端のもの」として毛嫌いしていましたが、ルネサンスの教皇たちは古代の遺品を買いあさるようになります。コイン収集に熱心であった教皇には、パウルス2世が有名です。
また、ヨーロッパの歴史には外せないメディチ家も、熱心にコインを収集しています。とくに、「フィレンツェの国父」として有名なコジモ・デ・メディチや、花の都フィレンツェのスピリットといわれるロレンツォ・イル・マニーフィコ・デ・メディチは、古代ローマのコインを数多くコレクションを残しています。
16世紀には中世のコインを収集する動きも
また、ペトラルカよりも半世紀ほど後に生まれたイタリア貴族フランチェスコ・ダ・カッラーラは、パドヴァが敵から解放されたのを記念してコインを鋳造しています。こうした記念コインの鋳造も、ペトラルカの後の時代に盛んになっていったのです。
16世紀に入ると古代のコインだけではなく、時代が近い中世のコインの収集を始める人が増えました。もちろん、それに伴って偽物も出回るようになるのですが、コインが時代の象徴として歴史学において重要な役割を果たすようになったり、アートの分野で注目されたりと、現代まで続くコイン収集のベースがこうした時代に生まれたことは興味深いですね。
最後に
イタリア文学の父とも称されるペトラルカ。ルネサンス(古代の再生)という時代の潮流にふさわしく、ペトラルカの興味は古代ローマに向きっぱなしでした。古代ローマ世界に少しでも近づきたいという彼の熱意が、当時の人々の手が触れたコインの収拾に向かったといってよいでしょう。
そして、彼がそれを意図したかしなかったかには関係なく、ヨーロッパにおけるコイン収集の祖は今もペトラルカというのが定説になったのです。彼の後に起こる本格的なルネサンスの時代に、コイン収集ブームを巻き起こしたその功績も大きいといえるでしょう。