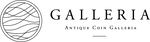ご利用は計画的にお頼み申す!~武士たちの借金事情~
現在、日本は財政赤字の状態が年々続き、
累積赤字国債の残高が増え続けている。
地方自治体レベルでも全体的に同様である。
また、個人でもローンなどの形で
借金を行なっている人も多いだろう。
これは、実は江戸時代でもあまり変わらない光景であったようだ。
大名から庶民に至るまで借金を抱えている。
江戸時代にはそんな歴史的側面もあるのだ。
今回はそんな徳川幕府時代の、
特に武士に絞って借金事情を覗いてみよう。
藩の財政事情

大名貸しで財を成した鴻池屋
まずは政治の主役、大名の様子はどうだろう。
大名、すなわち藩の歳入は
基本的に村方からの年貢米及び町方からの税の一種である
冥加金や運上金などであった。
歳出先としては大名の生活費、
家臣の俸祿、藩の政策費用といったところだ。
江戸時代初期はうまく財政は回っていたのだが、
次第に行き詰まりを見せてきた。
原因はいくつかある。
まず、参勤交代の費用がかさんだことである。
歴史の教科書では
参勤交代は謀叛を起こさぬよう藩の財政力をそぐためである、
と書かれているが、実際はそうではないらしい。
むしろ、「大名行列は身分相応でおこなうべし」という旨の
通達が幕府から出されていたくらいであり、
出費が藩財政に影響を与えるほどかさんだのは
威厳を見せつける、大名としての形式を整える、
といった目的から大名行列を飾りたてたことが原因の
言わば自滅である。

加賀藩「大名行列図屏風」
とはいえ、
名誉を重んじる武家が手を抜ける社会風土でも無かった。
さらに、参勤交代を行なうということは
領地の他に江戸にも邸宅を構えるということでもある。
すなわち別荘を置くということであるが、
ここの維持管理費用が必要だ。
また、領地から離れて事実上の首都江戸で暮らすとなると
交際費など様々な出費もでてくることになる。
また、参勤交代以外にも
幕府の命令による土木工事などにも費用がかかる場合もあり、
特別な出費を強いられることがあった。
更に藩の歳入源にも問題があった。
主力である年貢米は物納であったから、
カネを得るにはこれを売却する必要がある。
つまり、米相場に歳入が大きく左右されるというわけだ。
戦国時代が終わって平和が訪れ、
農業技術が進歩し、農地も増えると米の供給が増え、
自然と価格は下落する。
そうすると藩の歳入は大きく減ってしまうのである。
以上のようなわけで赤字財政に転落した藩は
借金をすることになる。
現代であれば公債を発行するところだが、
当時は民間の金貸しからカネを借りた。
貸し手になっていたのは裕福な商人、豪商である。
大名をめぐる借金事情
藩・大名を相手にした金貸し金融を大名貸しと呼び、
豪商は江戸では「金主」、大坂や京都では「銀主」と呼ばれていた。
大名貸しは、定期収入である年貢を返済のあてにできたため、
手堅い商売とみなされて活発に行なわれた。
大名側も豪商に武士待遇を認めたり、
特産品を贈るなど関係を深めていった。
ところが、いよいよ赤字財政が深刻化してくると
返済が滞るようになった。
いくらこちらが貸し手であるとは言え、
藩の支配者である大名とは社会的に絶対の上下関係にある。
踏み倒されてしまっても泣き寝入りするしかなかった。
予想に反して手堅い商売ではなかったのだ。
この踏み倒しにより、
大名貸しを行なっていた豪商が没落することもままあったという。
こうなってくると
リスクが大きい大名貸しを行なう豪商が減っていくのは道理だ。
しかし、藩は借金をしなければならない。
そこで、リスクを避けるべく貸主が藩の財政に参画したり、
百姓や農地を担保にカネを融通したりした。
財政に参画した豪商の中には、
いくつもの藩の財政を建て直した
山片蟠桃のような人物もいたのはこの時代ならではというところか。

山片蟠桃像
こんな状況に対し、
地方たる藩に対する中央である幕府は何もしなかったのか、
という疑問が生じるだろう。
一応、きちんと救済策は整備されていたようだ。
拝借金制度がそれである。
災害や財政難に対して幕府が無利息で資金を貸し出し、
年賦で返済するという仕組みである。
いざ、というときのセーフティーネットに幕府がなっていたわけである。
しかし、幕府自体の財政事情が悪化してくると
貸し出しを停止することもあった。
かの田沼意次は停止に踏み切ったことで
大名や旗本の評判を悪くしたらしい。
江戸の幕臣をめぐる借金事情
大名がこんな状態であるから、
家臣もまた大変であった。
江戸に住む幕府の家臣である旗本や御家人もまたしかりだ。
彼らが頼ったのは札差という業者である。
札差はもともと、
年3回の切米という幕臣の給料である米を受給する代理人であり、
現金化を代行する業者であった。

武士の俸給証書
つまり、札差は切米という給料を担保として
もともと押さえることかできる立場にあったわけだ。
こうして、先々の切米の一部を担保とし、
幕臣達は借金をするようになった。
しかし、財政難は慢性的だ。
借金は膨らむ一方である。
これを打破すべく、幕府は棄捐令をだした。
借金を強制的にほぼチャラにさせてしまったのだ。
この時点で帳消しにされた借金残高は約120万両とされる。
国家予算とも言える幕府の年間経費が約150万両であったから、
そうとうな額であったことがわかるだろう。
ただ、チャラにされてしまった札差はた大損失である。
もちろん、幕臣に融資しなくなった。
これはこれで困るというわけで、幕府は対策をとった。
まずは1万両を幕府から札差に直接貸し出しを行なった。
また、猿屋町御貸付金会所という札差専門の金融組織を立ち上げる。
これは幕府の御用商人が資金をだして設立され、
札差に年8%の金利で融資した。
札差はそれをさらに幕臣に年12%の金利で融資する。
猿屋町御貸付金会所の資金は形式上幕府の預かり金、
つまり公金となったわけで、信用度が増し、
安定した運用が行なわれたようである。
一応、拝借金制度のように幕臣向けにも救済制度があった。
御貸付金というのがそれだ。
年利4~5%と低金利であった。
しかしながら、これを利用するには審査が必要であり、
緊急時には役立たず、札差を利用するしかなかったようだ。
このように、江戸時代の武士は意外とカツカツの生活を行い、
借金漬けだったことがわかる。
ちょっと時代劇を見る目も変わってくるのではないだろうか。
ご利用は計画的にお頼み申す!~武士たちの借金事情~はアンティークコインギャラリア | 旧ナミノリハウスで公開された投稿です。