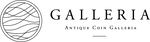日本以上!!歴史上のバブル→崩壊がスゴすぎた!
バブル景気といえば、
大半の日本人にとっては1980年代後半から1991年にかけて経験した
実体経済とかけ離れた未曾有の好景気を指すだろう。
しかし、このバブル景気のような現象は日本だけのものではない。
近年で言えばアメリカ合衆国のサブプライムローン問題も
似たような構造を持っていた。
人々が幻想にとらわれた投資をし続けた結果、
ついに現実との乖離が限界を越えて破綻するという
この「バブル」現象は市場経済がある以上避けられないのかもしれない。
それを証明するかのように、
近世欧州という市場経済黎明期の場でも同様の現象が起こっている。
今回は三大バブルと呼ばれた3つの事件を見ていこう。
史上初の「バブル」、チューリップ狂時代
17世紀、欧州の富裕層の間ではチューリップの収集が流行していた。
オスマン帝国からこの花が伝来したばかりの頃で、
異国情緒漂う富の象徴とされたのだ。
オランダは欧州の中ではチューリップの栽培に適した自然環境を持っていたため、
オランダ人達が資産家向けに球根を植え始めるのは自然な流れだった。
ところで、チューリップには花びらに珍しい模様がでることがあり、
これは大変高値で取引された。
これは球根の状態ではわからなかったため、
球根を買っておけば一攫千金も夢ではなかったのだ。
また、栽培に時間がかかるため、需要に供給が追いつかず、価格は上昇していった。

「無窮の皇帝」と呼ばれた最高価値のチューリップ。バブル時はこれひとつで大きな家が買えた。
当初、愛好家達の間でのみ取引されていたチューリップ球根だが、
こうした事情から投機家達に目をつけられ、投資対象となった。
また、金融商品の中では球根は比較的安価であったので、
農家や労働者といった一般庶民もこれに参加した。
先物取引もなされるようになり、オランダにおいて球根は凄まじい勢いで急騰した。
ピーク時には数週間で60倍になったという。
だが、突然この夢は終わりを告げる。
確たる理由は不明だが、あるとき買い手が全くつかないようになったのである。
球根価格は元の値段の半分以下にまで急降下し、
投資していた人々に破産者が続出したという。
この事件のインパクトは大きく、
しばらくの間、チューリップという単語は「バブル」の意味で使われるようになった。
高名な悪魔を産んだ、ミシシッピ計画
18世紀前半、フランスは
先代の王ルイ14世による浪費により多大な財政赤字を抱えていた。
そこに現れたのが経済思想家ジョン・ローである。
彼は不換紙幣、すなわち貴金属に交換可能とすることで価値を保証するのではなく、
政府が保証するなどして信用を保つ紙幣の導入を主張し、それが受け入れられた。
ルイ15世の認証のもと、ローはフランス初の紙幣を発行・管理する銀行、
すなわち中央銀行を設立、総裁に就任する。
新総裁の金融政策は北アメリカ大陸のフランス領ルイジアナ開発会社である
「インド会社(通称ミシシッピ会社)」の経営と抱き合わせで進められた。
彼はこの会社の総裁にも就任するのである。
ローはルイジアナを宝の山であると巧みに宣伝し、
これを信じたパリ市民達によってインド会社の株価は値上がりしていく。
インド会社株の配当金はもちろん中央銀行発行の紙幣で支払われた。

ローによって紹介されたルイジアナのキャンプ図
さらに、彼は市場価値が下落していたフランス国債をインド会社株と交換可能とする政策を打ち出す。
額面より低い価値しか持たなくなっていた国債から
値上がりと配当金が期待できるインド会社株に乗り換えられるということで、
人々は次々に交換に応じていった。

インド会社の株券
こうして、フランス政府の借金は事実上帳消しとなったのである。
ミシシッピ会社は幻想を産み続け、
投機もあって株価は20倍にまで上昇。
配当金の紙幣と株券とで市場の貨幣供給量は膨れ上がり、
フランスは空前の好景気となった。
しかし、夢とは醒めるものである。
インド会社の経営はうまくいってはいなかった。
ルイジアナは宝の山などではなかったのだ。
それゆえに取り付け騒ぎが発生したとき、インド会社は耐えきれなかった。
インド会社株は大暴落し、フランス経済は深刻な危機に陥ったのだ。
この一人の男がつくりあげた幻想とその崩壊の物語に影響を受けたとあるドイツ人作家は
後世に残る作品を執筆することになる。
タイトルは『ファウスト』、作家の名はゲーテである。
フランスがローの監督する舞台で踊っていたころ、
イギリスもまた戦費などで赤字財政を抱えていた。
そこで、国債を引き受けさせることを条件とした南米大陸との独占貿易権の入札を行った。
「バブル」の語源、南海泡沫事件
イングランド銀行や東インド会社との激しい競争に勝ち残ったのが
「南海会社」である。
しかし、実際には貿易業務で利潤は得られなかったようだ。
そこで、この会社は人為的にバブルを生み出す奇策を実行するのである。
まず、イギリス議会の承認を得て、
イギリス国債と南海会社株を交換できるようにした。
ここまではフランスのローと同様の手口だ。
ただ、交換レートを「南海会社株の時価=国債の額面」とし、
「国債引き受け価格と同額の”額面金額”の新株を発行する権利」を政府から得たのである。
額面100ポンドの株が200ポンドの株価となれば、国債200ポンド分と交換できる。
すると、会社は手に入れた国債200ポンド分の新株を発行できるようになる。
つまり、株を額面100ポンド増やせるわけだ。
この増えた100ポンドの株券を時価で売却すれば200ポンドとなり、
これはそのまま会社の利益となるのである。
会社の利益が上がれば当然株価は上昇する。
するとさらに新株を発行できるようになる。
一種の永久機関の誕生であった。
このカラクリを見ると狐につままれたような感覚にとらわれる。
理解しにくいのだが、少々頭の体操をしていただきたい。
この永久機関と独占貿易権への期待から人々の欲望を載せて
南海会社のみならず他の会社の株価も急騰していく。

南海泡沫事件の風刺画
しかし、この錬金術に危機感を覚えた議員たちが規制法を制定、
熱狂が鎮静化するとともに実は南海会社の実態を知っていた一部の投資家が資金を引き上げたことで大暴落が発生、
経済恐慌が発生したのである。

南海泡沫事件前後の株式チャート
この大暴落にはかのニュートンですら巻き込まれ、多大な損失を出したという。
また、このような会社を泡沫会社と呼んだことから、
以後実体背景のない好景気を「バブル」と呼称することになるのである。
日本以上!!歴史上のバブル→崩壊がスゴすぎた!はアンティークコインギャラリア | 旧ナミノリハウスで公開された投稿です。