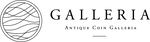身元保証人は金と銀!?お金が信用されていなかった時代
我々はさも当然のように毎日千円札や一万円札、
すなわち紙幣を利用している。
千円札には千円の価値があるわけであるが、
身も蓋もない言い方をしてしまえば少々柄が複雑なだけのただの紙である。
この紙切れを安心して日常で使用しているのは、
この紙切れの価値を日本銀行や日本政府が保証してくれているからに他ならない。
しかし、政府や銀行がそこまで信用できなかった、
あるいは信用を構築するためのシステムができあがっていなかった時代には、
別のやり方で紙幣の価値を保証していたのだ。
それは、紙幣を銀行に持っていけば、
同価値の貴金属と交換可能であるという保証方法である。
これによって、
例えば一万円札ならば一万円分の貴金属の価値を確かに有するということになり、
紙幣は保証されてのである。

銀と交換できた一円紙幣
金を機軸通貨と規定して紙幣と交換可能とする制度を金本位制度、
銀を基軸通貨とする制度を銀本位制度という。
誤解を招かないように言っておくが、
紙幣が使用されていない場合でも、金が基軸通貨であれば金本位制度とである。
今回は欧州において、
金本位制度と銀本位制度がどのように発達していったのか、
覗き見てみるとしよう。
金と銀が共に流通する時代
欧州においては8世紀頃に、
銀貨が基軸通貨である銀本位制度が始まったようだ。
ローマ帝国では金の貨幣も流通していたが、
この時代からは祭祀の際を除いてあまり鋳造されなくなった。
ここから6世紀ほどにわたって銀貨が商取引の主役であり続ける。
国境を越えた取引というものは少なく、
商業活動が比較的小規模であったのもその一因だろう。
銀に比べて価値の高い金の出番は無かったというわけだ。
各国は同一基準の通称デナリウス銀貨を発行し、
それで貨幣の流通を間に合わせていた。
約1.5グラム程度の小型貨幣である。
1円玉が1グラムであると言えばその小ささがわかるだろう。

デナリウス銀貨
余談であるが、
デナリウス銀貨とは本来ローマ帝国が発行していた銀貨であり、
その名称を受け継ぐ形で
現代におけるフランスの前身であるフランク王国が発行を始めたとされる。
さて、中世も後半に差しかかり、
次第に各国の経済が発達してきて特に国境を越えた商取引の規模が拡大してきた。
少額のデナリウス銀貨では間に合わない事態になってきたのである。
そこで、13世紀半ばから14世紀半ばにかけて
欧州各国は金貨の鋳造を再開する。
これは各国独自の基準でつくられた。
例えば、イタリアのフローリン金貨やハンガリーのフォリント金貨が有名だ。

フローリン金貨
また、16世紀半ばには
ターレル銀貨と呼ばれる大型銀貨も国際決済用に鋳造され始めた。
これは各国同基準でつくられ、国際基軸通貨として広く通用した。
「ターレル」はアメリカ合衆国の通貨単位「ドル」の語源ともされている。
この名称は国際基軸通貨たることを運命づけられているのかもしれない。
金貨やターレル銀貨が流通していた時代、
国際決済ではこれらの貨幣が用いられたが、
国内では依然としてデナリウス銀貨が用いられていた。
通貨が二重構造を有していたということになる。

ターレル銀貨
言ってみれば、金本位制度と銀本位制度が並立していたということになる。
この状態は19世紀、各国の産業革命が終わるころまで持続する。
金の大量獲得と金による覇権
金本位制度と銀本位制度の併存には弱点があった。
その交換比率をめぐる問題だ。
金貨と銀貨はその交換レートが法で定められていたが、
実際の金銀の市場価値は異なってくる。
例えば、法定レートが金貨1=銀貨10だとしよう。
しかし、市場で金の価値が下落し、金1=銀5の価値になったとする。
この場合、金貨を盛んに鋳造して法定レートで銀貨と交換し、
その銀貨を鋳つぶして地銀にしてしまえば市場価値の半値で銀を手にすることができる。
その結果、銀貨の流通が少なくなり、金貨が多く流通してしまうことになる。
この現象により、市場の混乱や商取引の煩雑化等しばしば不都合が生じた。
各国がそれぞれ充分な量の金や銀を保有していれば
どちらかに統一できたのだろうが、
当時の欧州にはそれだけの金銀が存在しなかった。
それが変化していくのが19世紀である。
欧州によって植民地化されていたアメリカ大陸から
金の流入が始まったのである。
19世紀中盤のカリフォルニアで発生した
ゴールドラッシュによってそれは加速するが、
それ以前はブラジルからの流入が主であった。

ブラジルのオウロ・プレット金鉱跡地
当時、ブラジルはポルトガルの植民地であり、
金は主に宗主国に入ってきた。
ポルトガルはイギリスとの間に貿易赤字を抱え、
支払いをブラジル金で行なったため、イギリスにも金が流入してくるようになった。
充分な量の金を手に入れたイギリスは
欧州各国に先駆けて1816年に金本位制度を採用、
ポルトガルも1854年にそれに続いた。
また、普仏戦争の賠償金で大量の金を手に入れたドイツも
1871年に金本位制度を採用、
その後銀価格が下落したことで
既に充分な金を手に入れていたフランスやベルギーもそれに続くことになった。
19世紀後半はすでに全世界的な商業活動がなされるようになっていた。
ヨーロッパの経済大国が次々と金本位制度に転換するに至り、
円滑な決済がなされるよう、その他の国々も金本位制度を採用することになった。
日本もそのひとつだ。
また、遠距離で莫大な価格の取引を行なうために
いちいち金を大量に輸送するのは大変効率が悪いということで
紙幣が発行されるようになった。
金との交換が保証されたものだ。
こうして、
金の全世界的な流通量の増加及び欧州の経済成長によって、紙幣社会が誕生したのである。

初期の1ドル紙幣
身元保証人は金と銀!?お金が信用されていなかった時代はアンティークコインギャラリア | 旧ナミノリハウスで公開された投稿です。