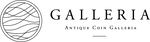「一円玉」が5,000円? 時代にひっくり返される現物資産の価値
中学時代のことだ。
数学の先生が何かの雑談ついでにこう言ったのを覚えている。
「君らは道にお金が落ちてたら何でも拾うかもしれないがな、
落ちてるのが一円玉だったら、拾う分のエネルギーの方が無駄になるんだぞ」
誰が言い出したか知らないが、
似たような記述を本でも目にしたことがあるので世間では広く知られた話なのだろう。
本当にエネルギーが一円分以上浪費されるのかは知らないが、
当時の私は「そんなものかな」と思った。
周りのクラスメイトもそうだったろう。
「一円玉だし、その程度の価値しかないよな」と。
これは世間一般の反応と近いだろう。
今の日本で「一円玉」の評価はその程度である。
消費税や釣銭の端数合わせ程度しか用いられない。
実際、一円玉を製造すると一枚につき13円の赤字が発生するという話もあるし、
保管コストがかかるので金融機関もあまり引き取りたがらないとか、
完全に厄介者扱いである。
ここでもし「一円玉を資産として保持したらどうか」
と言われたらほとんどの人は笑うだろう。
日頃金相場などに敏感で、
貴金属に資産価値を認めてる人でもきょとんとするに違いない。
「なんのために? アルミを何かに使うのかい?」などと。
大部分の人はこうした一円玉――素材としてのアルミ――を軽んじる姿勢が、
あくまで現代の視点という事に気付いていない。
実は人類史ではアルミニウムを立派に「資産」と
みなしてよい時代があったのである。
そしてそれをめぐる話は現物資産としての「鉱物」の価値について、
根源的なものに気付ける糸口となるものである。
一時は「宝物」だったアルミニウム
八十年代、故竹下首相が始めた「ふるさと創生事業」では
全国の自治体に一億円ずつ配られ、使い道は自由裁量に任された。
兵庫県旧津名町(現淡路市)では、
創生資金で「金塊」を購入して公園に設置したが、
これは大変な人気を呼び公開以来360万人の見物客が訪れたという。

静の里公園の金塊
同じ金でいえば、
金箔の貼りめぐらされた金閣寺は世界的にも有名で
日本の観光地としてはトップクラスの知名度を誇る。
また酒好きの人なら、
清酒に金箔のかけらを浮かべて飲んで、贅沢な気持ちを味わう飲酒趣味をご存じだろう。
いずれも「金」の醸し出す魅力――贅沢感や豪華さ――が人々を惹きつけているのである。
しかしこの「鉱物の王様」よりも格上だったのがアルミだというと驚かれるだろうか。
高度に近代的な金属

アルミ缶
意外にもアルミの歴史は新しい。
きちんとアルミニウムが単体の金属として認知されようになったのは
18~19世紀頃である。
金や鉄は古代から人類の歴史とともにあったのに、
なぜアルミはこうだったのか?
答えは金属としての性質にある。
化学的に難しく言うと「イオン化しやすい」。
要するに他の元素と化合しやすく、
ミョウバンやボーキイトに含まれていても
単体として分離させる技術が未発達だったのである。

精錬前のボーキサイト

ミョウバンの結晶
19世紀頃になるとアルミだけを取り出す化学的な精錬法が生まれてきたが、
まだまだ非効率でコストがかかった。
その分アルミニウムの価値は高くなり、
金や銀よりも貴重で高価となったのである。
高級品となると人々もそのように扱う。
ヨーロッパの貴族や富裕層の間では
アルミニウムは一種のステータスシンボルのような位置づけにもなった。
アルミで作ったフォークやナイフを晩餐会で見せびらかしたり、
貴婦人がアルミを貼った扇子を携えたり、
コレクターがアルミを珍品として大事にするようにもなる。
ナポレオンの甥のナポレオン三世はとりわけアルミを愛し、
儀礼用の兜や服のボタンをアルミで作らせたという。

アルミの扇

三世のアルミの兜
三世は普通のお客は金や銀の皿でもてなし、
VIPが訪れた際にはアルミの皿で饗応したそうである
(ちなみに我が国の徳川昭武が使節団としてパリを訪れた際、
アルミの棒を特別に見せてもらったとの記録が残る)。
当時のパリ万博では「アルミの延べ棒」が目玉の品として出品され
来訪者に大人気であったという。
つまり今日のわれわれが、
金塊やツタンカーメンの黄金のマスクを見て惚れ惚れするのと同じような気持ちを、
当時の人々はアルミを見て味わっていたのである。
現在のように氷晶石を触媒にした電気分解法のアルミ精錬技術が確立される前は、
このような状況だったのである。
「資産」自体の価値も変動する
現在の「アルミニウム」に関する人々の感覚を考えてみよう。
アルミ箔は弁当のおにぎりやお菓子の包み紙程度の扱いである。
使い終わったら即ゴミ箱行きだ。
アルミの塊を見世物にしても、
300万人を超える集客力など夢のまた夢である。
そう、科学技術の発達で大量生産が可能になり、
人々の価値観が変わってしまったのである。
有名な17世紀オランダのチューリップバブル(チューリップが大流行して値段が暴騰した)では、
珍しい球根は時に別荘や馬車とまで交換されたという。

チューリップ
結果としてバブルが弾けると、
球根の山だけが手元に残り途方にくれる人が続出したそうである。
古代、「ガラス」製造技術がまだ秘法であった頃、
ローマ皇帝はガラス器を黄金をはたいて買い、
我が国に伝来すると珍宝として正倉院の宝物庫に大切に蔵われた。
しかし今やガラスのコップなど一山いくらだ。
アルミも大量生産が可能になると、価値は初期の数千分の一程度にまで暴落した。
「資産」としてアルミの品々を所持していた人々は、
チューリップの球根を抱えて途方にくれた投機家や、
売れないマンションが手元に残った不動産屋と同じ立場になったのだ。
往時のナポレオン三世の贅を凝らしたアルミの品々も、
あるのは骨董的な価値である。
現物資産としての永続性
今日われわれは金銀やジュエリーを尊ぶ。
趣味や服飾のためだけではなく、
いざという時の「資産」の意識で購入する人も多い。
清朝のラストエンペラーだった溥儀は、
国が崩壊して逃亡するさなかも貴重な宝石箱を肌身離さなかったそうである。
ユダヤ人に宝石を扱う人材が豊富だったのも、
流浪の民で資産を守る必要があったためとはよく言われる。
金銀鉱物は古代から続いた「現物資産」の代表格である。
単純に否定すべきものではないが、
一度立ち止まって考えてみるのもよいだろう。
その鉱物の価値は永遠か。
技術発達や国際政治の荒波を乗り越えられるものか。
かつて貴族の高級品だった真珠は
日本が技術革新で養殖真珠の育成に成功したため、
生産量を飛躍的に伸ばした。
結果価格も下がり、「資産」としての強みは乏しくなった。
ダイヤモンドも実は生産量だけはそれなりにあっても、
人為的な価格調整がなされていることは有名である。
これは一時的な国際的な価格競争が起こりかけて価値が暴落しかかったため、
国際的なカルテルによって、高値維持のコンセンサスが出来たためである。
生産と流通ルートの規制と談合の力によるものであって、
ダイヤそのものの力ではない。
さいごに
金にしろダイヤにしろ鉱物系資産の外見は輝かしく人の目を打つ。
現在の人々の評価とその煌びやかさのため、
つい物そのものに不変的な価値が備わっているかのように誤解しがちだ。
しかしそれはあくまで時代の枠組みの中で、
限定されて成立する価値なのかもしれない。
アルミはかつて「粘土から生まれた銀」とまで呼ばれて持ち上げられた。
しかしその輝きは永遠だったか。
財布の中の邪魔な一円玉を手にした時は一度過去に思いをはせてみよう。
ひょっとするとそれが賢い「現物資産の持ち方」につながっていくかもしれない。

アルミ製の水筒
「一円玉」が5,000円? 時代にひっくり返される現物資産の価値はアンティークコインギャラリア | 旧ナミノリハウスで公開された投稿です。